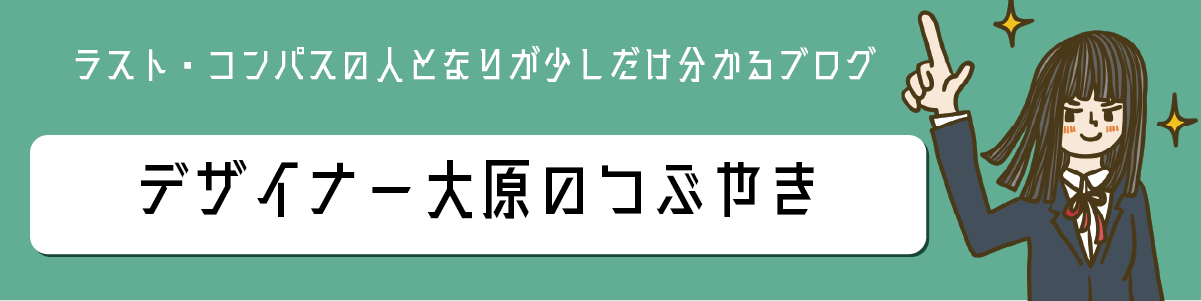 こんにちは、ラストコンパスの大原です。
タイトルについて。
学生時代の学びで、今も意識していることです。
私は、野球少年やサッカー少年といった
言い方に倣えば、美術少女でした。
始発に近い電車に乗って
朝1時間かけて学校へ行き、授業まで絵を描いたり、
年末年始には大きな作品を持ち帰って
紅白を見ながらリビングで制作したりする。
そんな学生時代でした。
みんなが大学入試に向けて参考書や赤本に苦心しているとき、
私もそれに加えて静物デッサンに打ち込んでいました。
(静物デッサンとは、モチーフ(描く対象のもの)を
自分で構成して並べ、
鉛筆や練り消しなどで描写するものです)
(地域や目的、受ける学校により多少異なりますが、
ここでは省略します)
大抵の場合、デッサンなど何かを作るとその後講評会があり、
先生方から直接フィードバックを受けます。
面白い先生方が多く、色々な指導を受けましたが、
・「セロテープのギザギザの個数まで考えたか?
それぐらいの目を持ちなさい」
・「あなたが見ていないものは描けない。
先生が髪を切ったって、スカートを履いてたって
認識できていないなら描きようがないでしょう。」
(※男性の先生)
…など、思い返すと
かなりクセの強い発言が多かったなと思います。
その指導の中で今でも影響を受けているのが、
タイトルの言葉です。
どんなクセの強い先生でも、のんびりした先生でも、
高校でも大学でも、どこでも繰り返し言われました。
デッサンは鉛筆などでグレースケールだけを用いて、
色や陰影、細かな部分まで表現します。
こんにちは、ラストコンパスの大原です。
タイトルについて。
学生時代の学びで、今も意識していることです。
私は、野球少年やサッカー少年といった
言い方に倣えば、美術少女でした。
始発に近い電車に乗って
朝1時間かけて学校へ行き、授業まで絵を描いたり、
年末年始には大きな作品を持ち帰って
紅白を見ながらリビングで制作したりする。
そんな学生時代でした。
みんなが大学入試に向けて参考書や赤本に苦心しているとき、
私もそれに加えて静物デッサンに打ち込んでいました。
(静物デッサンとは、モチーフ(描く対象のもの)を
自分で構成して並べ、
鉛筆や練り消しなどで描写するものです)
(地域や目的、受ける学校により多少異なりますが、
ここでは省略します)
大抵の場合、デッサンなど何かを作るとその後講評会があり、
先生方から直接フィードバックを受けます。
面白い先生方が多く、色々な指導を受けましたが、
・「セロテープのギザギザの個数まで考えたか?
それぐらいの目を持ちなさい」
・「あなたが見ていないものは描けない。
先生が髪を切ったって、スカートを履いてたって
認識できていないなら描きようがないでしょう。」
(※男性の先生)
…など、思い返すと
かなりクセの強い発言が多かったなと思います。
その指導の中で今でも影響を受けているのが、
タイトルの言葉です。
どんなクセの強い先生でも、のんびりした先生でも、
高校でも大学でも、どこでも繰り返し言われました。
デッサンは鉛筆などでグレースケールだけを用いて、
色や陰影、細かな部分まで表現します。
初心者がよく陥りがちなのが、
例えばりんごとコーラを描く課題が出たとして。
りんごの赤と瓶コーラの黒を描きわけなければいけない。
その時に瓶の影の部分、
光が当たっている部分をコーラ単体の内部でも描きわける。
りんごもとにかく暗いところの色を落としていく。
やみくもにただ描いていく。
すると、仕上がった時には
「あれ?コーラとりんご、同じ色味になってない?」
「コーラだけ、なんか暗すぎない?」
「細かい描写はいいとして、立体感なくない?
平面的じゃない?」
…と。まあ大抵の場合狂います。
やっていること自体は正しいのですが、
一つの観点が抜けている。
それが「細部と全体を見る」ことです。
ある程度形が取れたら離れて全体を見る。
細かなところを描写したら離れて全体を見る。
新しいパーツを描いたら離れて全体を見る。
とにかく何か描いたら「全体を見る」
するとそのときに、
「ここに比べるともっと暗くしなければ」
「このコーラ、なんか大きくない?バランスが悪くない?」
「ここだけこれだけ描いたなら、
こっちも同じくらい描かないと」
…と、理想像に対しての欠点を冷静に見つけられます。
そしてその改善に向けて次の手を打てる。
そうした繰り返しで一つの作品ができあがっていきます。
先生方は、それが良いものを作るための
究極のポイントだと理解していたからこそ、
繰り返し私たちに伝えてくださったのだと思います。
大人になった今、
これはすべてのことに通じると考えています。
例えば仕事をするとき、
大きな流れや計画・目標があるとして、
日々の小さな業務が積み重なって一つの成果を生みます。
小さな業務に全力で取り組んだとしても、
目標を振り返らなければ
最終的に目指すものからずれたり、
不必要に時間を費やすことになりかねません。
今行っていることが全体のどこに位置しているのか。
他のことにどう影響するのか。
何かを行ったら立ち返って整理する
──「全体を見る」ことに時間を取る。
それが物事を良くしていくことに繋がると思います。
私は作品制作という技術面を学びながらも、
物事に向き合う基本姿勢を美術から学んでいたのだと、
改めて社会で生きる中で感じています。
今はまだ仕事に慣れ、深く理解していくフェーズで、
全体を掴むことに必死な場面もありますが、
闇雲に進めるのではなく、余裕を持って
振り返りながら取り組んでいきたいと思います。
大原
こんにちは、ラストコンパスの大原です。 タイトルについて。 学生時代の学びで、今も意識していることです。 私は、野球少年やサッカー少年といった 言い方に倣えば、美術少女でした。 始発に近い電車に乗って 朝1時間かけて学校へ行き、授業まで絵を描いたり、 年末年始には大きな作品を持ち帰って 紅白を見ながらリビングで制作したりする。 そんな学生時代でした。 みんなが大学入試に向けて参考書や赤本に苦心しているとき、 私もそれに加えて静物デッサンに打ち込んでいました。 (静物デッサンとは、モチーフ(描く対象のもの)を 自分で構成して並べ、 鉛筆や練り消しなどで描写するものです) (地域や目的、受ける学校により多少異なりますが、 ここでは省略します) 大抵の場合、デッサンなど何かを作るとその後講評会があり、 先生方から直接フィードバックを受けます。 面白い先生方が多く、色々な指導を受けましたが、 ・「セロテープのギザギザの個数まで考えたか? それぐらいの目を持ちなさい」 ・「あなたが見ていないものは描けない。 先生が髪を切ったって、スカートを履いてたって 認識できていないなら描きようがないでしょう。」 (※男性の先生) …など、思い返すと かなりクセの強い発言が多かったなと思います。 その指導の中で今でも影響を受けているのが、 タイトルの言葉です。 どんなクセの強い先生でも、のんびりした先生でも、 高校でも大学でも、どこでも繰り返し言われました。 デッサンは鉛筆などでグレースケールだけを用いて、 色や陰影、細かな部分まで表現します。