優秀な会社が人事評価制度の運用に失敗する理由
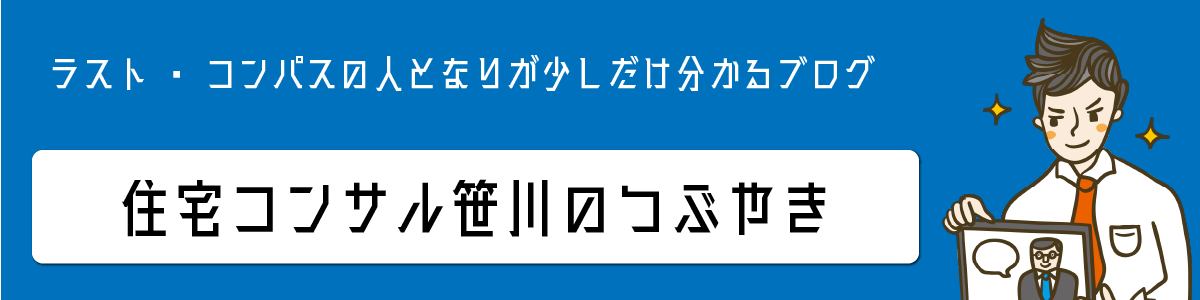
みなさん、こんにちは。
ラストコンパスの笹川です。
今回も前回に引き続いて、人事評価制度に関して記載していければと思います。
テーマは「人事評価制度の運用に失敗する理由」です。
特に、”優秀な会社”が陥るケースについて・・
まず1つ目は、「作り込みすぎる」です。
弊社にご相談いただく多くの会社様がおっしゃるのが、「以前、自社で人事評価制度を構築したが、今は全然使えていない」ということです。その理由としては、査定にかかる労力が重すぎて管理職が運用できずに諦めたり、制度が複雑すぎて社員が内容を理解していないために浸透しなかったりと様々です。例えば、住宅営業の評価軸として「受注棟数」を入れたい。でも、それだけだと値引きして棟数だけ伸ばすかもしれないから「受注額」と「利益額」も入れる。ただ、営業マンによっては紹介受注が多い人物もおり、これは広告費用が掛かっていないために価値は高く設定しよう。会社反響からの受注と紹介からの受注とで価値を変えて評価に反映するために、前者は1棟として換算し後者は1.5棟換算して評価に入れる。また、受注までの過程も評価したいので毎月どのような動きをして顧客にアプローチしたのかを履歴として残して評価材料にする等々・・
このように公正さと運用負担は矛盾し、優秀な会社ほど頓挫する可能性も上がっていきます。
どんなに時間を使って作り込んだとしても、そもそも運用できなければ意味がない。
2つ目は、「人の意見を聞きすぎる」です。
人の良い、優秀な会社の経営者様ほど社員の意見をしっかり聞いて、その多くを評価に反映してあげたいなと思われています。しかし、最初は良心で評価軸を拡充しても、時間が経てばその制度が不公平の温床になっていってしまうことも多いです。例えば、半期でAさんが10の要望を上司に伝えその内3つが評価に反映されて、Bさんが半期で5の要望を上司に伝えて1つがその方の評価軸に追加されたとします。その結果として、Aさんの評価が良くなる場合にはBさんの不満となり、不満が継続すれば人事評価へ興味を持たなくなり頓挫します。Bさんがやっている業務でも評価に反映されていない、かつ、Bさんが自己主張を苦手としている場合には不満が溜まりやすいです。実務が担当ごとに分かれていれば上司がBさんの実務を把握しづらいために猶更です。さらに言うと、AさんがBさんに雑務を押し付けて、Aさんは評価に入っている内容しか実施しない、Bさんは評価されない業務ばかり担当している、なんて状況も生まれてくるかもしれません。
言ったもん勝ちの雰囲気が会社の文化を壊していく。
3つ目は、「目標管理をしすぎる」です。
一見、目標管理をこまめに実施すると良さそうですが、なぜ人事評価にブレーキをかける事があるのでしょうか。それは、目標管理が「うざい」と思われることがあるからです。人事評価を行うプロセスにおいて、進捗確認や面談が必要ですが、その際の確認の仕方を誤れば、ネガティブな印象を生んでしまい、被評価者は5分後には評価に興味を失っているかもしれません。また、目標設定の仕方も大いに影響があるかと考えています。例えば、「ベテラン営業マンと新人」、「注文住宅の担当と企画住宅の担当」、「マネジャーとプレイヤー」、「設計営業担当と営業担当」等は、安易に同じ目標設定をすると思わぬ落とし穴になることがあるようです。
言われすぎると、人はやらなくなる
今回は、「優秀な会社が人事評価制度の運用に失敗する理由」に関して考えてみました。
あくまで一部の会社様の実体験になりますが、ご紹介させて頂きました。
それでは失礼いたします。
笹川