スーモカウンターを最大限活用する3つの鉄則
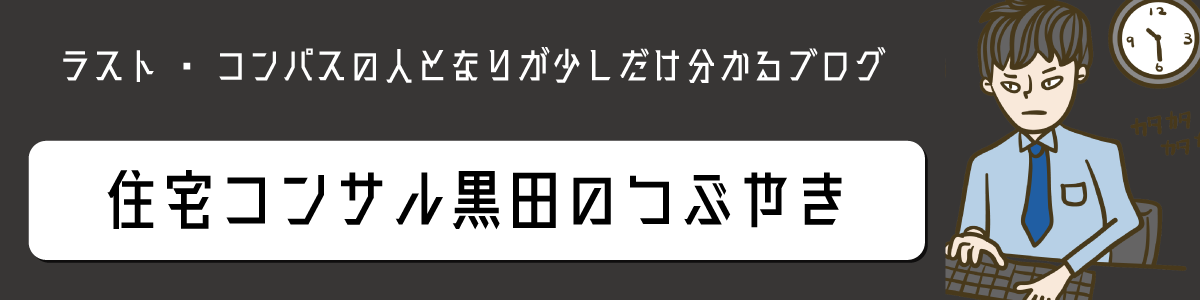
お世話になっております。
ラストコンパスの黒田です。
今年も桜は一瞬で散ってしまい、結局見ること叶わずでした。
毎年、花見をしようとしても仕事に夢中でいつも忘れます。
さて、今回は表題の通り、スーモカウンターに関するお話です。
今回の内容は、
・これからスーモカウンターを活用しようと思われている会社様
・現状スーモカウンターを活用しているものの、理想とする成果を得られていない会社様
に是非ご覧いただきたい内容です。
実際に住宅営業をしていた方から聞いた話も含んでいますので、ご参考にしていただけるのではと考えています。
■ スーモカウンターに来る顧客は“効率重視型”
まず理解しておきたいのは、スーモカウンターを訪れる顧客の心理です。
「建築会社選びが難航している」
「知識がなくて不安」
「自分たちに合った担当者を紹介してほしい」
「正しい予算感を知りたい」
このような背景を持ち、「効率よく」「間違いのない選択をしたい」と考える方がほとんどです。
そうでなければ、わざわざ紹介手数料を払ってまでスーモカウンターには行かないですよね。
つまり、担当者ガチャ(当たり外れ)を避け、中立な立場のスーモレディに“失敗しない選択”を求めているということです。
「コスパ・タイパ」という言葉が若者の中で使われていますが、家づくりにおいてもそうした考え方を持つ顧客が増えています。
■ スーモカウンターにおける3つの鉄則
ここからは、スーモカウンターを通じて契約率を高めるために、経営者、及び住宅営業担当者が実践すべき3つの鉄則をご紹介します。
① エース営業マンを投入する
スーモカウンターで紹介される建築会社は通常3〜4社になっており、
顧客は店長・支店長クラスが接客することが主流になっています。
というのも、スーモカウンターの契約理由で最も多いものが「担当者の人柄・信頼感」だからです。
つまり、ここに経験の浅い営業マンをあてがうことは大きな機会損失になります。
スーモレディも紹介先の成果にノルマがありますので、「成約しそうな営業」を見極め、営業力のある営業マンに顧客を紹介します。
エース営業マンを起用しなければ、満足に紹介すらしてもらえなくなる可能性があるのです。
② スピード対応で“1番手”を勝ち取る
先程、3~4社ほどの建築会社を紹介するとお伝えしましたが、何番目に接客した会社の契約が一番多いと考えられるでしょうか?
従来、契約に至るのは「最後に提案した会社」とされてきました。
しかし最近では「1番手で提案した会社で即決」も増えています。
なぜなら、冒頭でもお伝えした通り、スーモカウンターの利用者は「効率よく進めたい」という意識が強いので、良い担当に最初に出会えれば他を見る理由がなくなるのです。
また、スーモレディにも「○ヶ月以内に契約しないとノルマに反映されない」ということもあり、後回しの会社には不利な空気が生まれやすいです。
そのため、紹介後のスピード対応(即日面談調整、即時資料送付、即レス)ができないと、顧客の家づくりの土台にすら乗れない可能性があります。
③ 競合は“会社”ではなく“担当者”
スーモ経由で紹介される競合会社は、ある程度固定されています。
なぜなら、顧客の要望に沿った会社を紹介することになるので、ある程度同じような家づくりをしている会社が競合になりやすいのです。
つまり、競合する担当者もある程度固定されているということです。
競合排除で重要なことは競合会社の対策ではなく、
「この担当者は価格訴求型」「この人は土地知識に強い」など、担当者の提案傾向を徹底的にリサーチし、自社の営業マンが“その上を行く提案”をぶつけられるように対策することです。
商品・金額勝負ではなく、“担当の提案力と人間力”が勝負の決め手です。
■ スーモカウンター活用は“営業戦略の一環”である
スーモカウンターの面談から契約に至る率はおよそ15%です。
決して高い数字とは言えませんが、戦略を立てれば確実に勝率は上がります。
紹介された段階で「どう動くか」を営業側が設計できているかどうかで、結果は大きく変わります。
紹介して終わりではなく、エース起用、スピード、競合分析という“3つの武器”を磨き、
スーモを単なる集客窓口ではなく、「高精度なフィルターを通った顧客との出会いの場」として活用していくことをお勧めします。
住宅業界は今、大きな転換点にあります。
人口減少と市場の縮小により、従来の集客力だけでは受注を維持するのが難しい時代に突入しています。
このような状況の中、必要なのは「集客力の強化」ではなく「営業力の強化」ではないかと考えています。
今回の内容が貴社にお役立ていただければ幸いです。
ラストコンパス 黒田