母集団形成が難しくなった今必要なこと
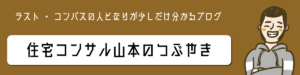
こんにちは。
ラストコンパスの山本です。
近年、新卒採用市場は大きく変化しています。
以前に比べ、母集団形成自体が難しくなり、エントリー数や説明会の参加者数に悩まれる企業様も増えてきました。
このような状況だからこそ、「誰でもいいから採用する」のではなく、
「本当に自社に合う人材を見極める力」がますます重要になっています。
そこで今回のテーマは「構造化質問」による面接の精度を高めるための考え方について、お話したいと思います。
構造化質問とは?
構造化質問とは、あらかじめ準備した質問内容と評価基準に基づき、全候補者に対して同じ質問を行う手法です。
これにより、面接官ごとの差を最小限に抑え、客観的でブレない判断が可能になります。
従来型の、場当たり的な質問ではどうしても面接官の感覚や主観が入りがちです。
特に、経験の浅い面接官が増えている企業では、評価のバラつきが課題となっている背景があります。
構造化質問は、こうした問題を解決するための有効な手段となります。
なぜ今、構造化質問が必要なのか
これまでは、数多くの母集団を形成できたため、多少のミスマッチがあっても「採用数」でカバーできていた面もあります。
しかし、これからの時代は違います。
・母集団そのものが小さい
・応募者一人ひとりの選考にかける重みが増している
・採用失敗=組織の生産性低下に直結する
だからこそ、面接の精度を高め、「本当にマッチする人材」を確実に見極める必要があります。
構造化質問は、そのための「仕組み作り」ともいえます。
構造化質問の進め方
具体的には、次のステップを踏んで構造化質問を設計していきます。
- 求める人物像を明確にする
→ 自社で活躍している人材の特徴を分析し、求めるスキル・志向性を整理する。 -
質問内容を統一する
→ 全候補者に対して「過去に困難だった経験」「チームで意見が割れた際の対応」など、
具体的な行動に焦点を当てた質問を設定する。 -
評価基準を設定する
→ 「単なる回答内容」ではなく、「どう考えたか」「どんな行動を取ったか」を評価軸にする。 -
面接官トレーニングを行う
→ 誰が面接しても一定の評価ができるよう、面接官同士でロールプレイングや基準のすり合わせを実施する。
こうした準備を行うことで、表面的な印象に惑わされず、本当に欲しい人材を見極めることが可能になります。
例えば、「主体性」を評価したい場合は以下のような質問になります。
・「学生時代に、自ら課題を見つけて取り組んだ経験を教えてください」
・「その課題に対して、どのような行動を取りましたか?」
・「その結果、どのような成果が得られましたか?」
このように、具体的な行動や結果を掘り下げることで、応募者の特性をより正確に把握することができます。
母集団形成が難しくなる今こそ、採用の「量」から「質」への転換が求められています。
構造化質問を取り入れることで、選考のバラつきを抑え、納得感ある採用ができるようになります。
まだ導入されていない方は、ぜひ一度、自社の面接プロセスを見直してみてはいかがでしょうか。
ラストコンパスでは、こうした採用における仕組み作りのご相談も承っています。
ご興味のある方は、お気軽にご相談ください。
山本