「振り返る習慣」が組織と個人を強くする
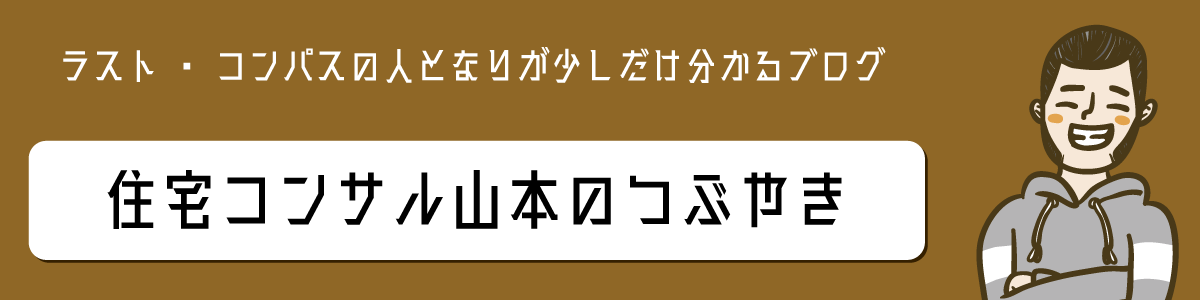
こんにちは。ラストコンパスの山本です。
皆さんは、日々の業務やプロジェクトの後、「振り返り」をしていますか?
仕事が忙しいと、どうしても終わった瞬間に次へと意識が向いてしまいがちですが、
私はこの“振り返り”こそが、成長において欠かせない習慣だと考えています。
今回は、個人として、組織として、なぜ振り返ることが大切なのか。
そして、どうすればそれを仕組み化できるのかについてお話しします。
「やりっぱなし」にしない文化をつくる
私たちの仕事は、常に“進行形”です。
営業も採用も、建築現場も、プロジェクトも、やったら終わりではなく、
改善を重ねることで精度が上がっていきます。
しかし、振り返りの時間を取らないと、
「次はどうすればもっと良くなるか?」が曖昧なまま終わってしまいます。
これでは、せっかくの経験も“消費”で終わってしまうのです。
たとえ結果が良くても悪くても、
「何が良かったのか」「何を変えるべきか」という視点で一度立ち止まること。
これが継続的な成長には不可欠です。
振り返りがもたらす3つの効果
私自身、前職の教員時代から「振り返り」を意識してきました。
授業を終えたあと、「うまく伝わらなかったのはどの場面か」「子どもたちが集中していたのはいつか」などを毎回書き留めていました。
この経験から、振り返りには以下の3つの効果があると実感しています。
- 成功体験を言語化し、再現可能にする
→ たまたまうまくいった、で終わらせない。次も同じ成果を出すために何が効いたのかを整理できます。 - 課題や失敗の原因を可視化する
→ 結果が出なかったとき、そのまま次へ進むのではなく、何が要因だったのかを分解しておくことで次に活かせます。 - チーム内の共通認識を育てる
→ 振り返りは、個人だけでなくチームで行うことで、「あの時どう感じていたか」が共有され、次の連携にも良い影響を与えます。
振り返りを“仕組み化”するという視点
とはいえ、「毎回反省会を開くのは難しい」「忙しくて時間がない」という声もあると思います。
そこで大事なのが、仕組み化という視点です。
たとえば、以下のような形で無理なく取り入れることができます。
- プロジェクト終了時に10分だけミニレビュー
- 社内チャットに「今日の気づき」投稿ルールを設ける
- 定例ミーティングの冒頭5分で“先週の振り返り”を行う
ポイントは、“完璧な反省会”を目指すのではなく、“小さくても継続的に振り返る文化”を育てることです。
小さな修正を積み重ねた組織は強い
振り返りがある組織は、自然と“前向きな修正”が得意になります。
その結果、挑戦しても失敗を恐れず、次のアクションがどんどん加速していく。そんな良い循環が生まれます。
逆に、振り返りのない組織では、「うまくいかなかった理由」が誰の中にも残らず、同じ失敗が繰り返されます。そして、それを“誰かのせい”にしがちになります。
だからこそ、振り返りは“責任追及”ではなく“改善の文化”であるという共通認識を持つことが大切です。
忙しいからこそ、あえて振り返る。
成功しても、失敗しても、「次につなげる」ことを意識する。
これは個人にも、組織にも、共通して必要な習慣です。
皆さんの職場では、日々の活動を「次に活かす仕組み」はありますか?
もし少しでも不安があるようでしたら、
まずは5分間の「気づき共有」から始めてみてはいかがでしょうか。
小さな一歩が、継続的な成長をつくります。
山本